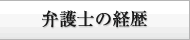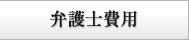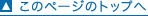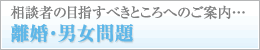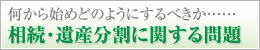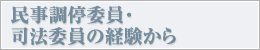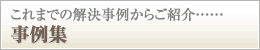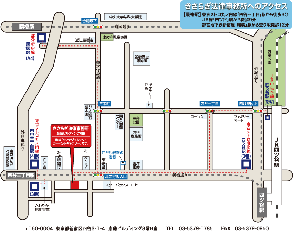相続人の範囲と相続分について
(2020/04/28)>> 一覧に戻る
相続が発生した場合、誰が相続人なのかがスタートです。
民法(887条等)に規定があります。配偶者は常に相続人となり、これに並ぶ相続人には順位があります。子が第1順位で、子がいない場合は親、親がいなければ兄弟姉妹となり、常に相続人となる被相続人の配偶者と相続分が定められています。
配偶者と子の場合は、1対1です。相続発生より前に子が死亡していた場合は、その子(被相続人の孫)が子(孫の親)の地位を承継して相続人となります。これを代襲相続と言います。
同順位の相続人間では――例えば被相続人の長男・長女・二女等――法定相続分は同じです。つまり、被相続人の配偶者と子3人が相続人の場合、配偶者が2分の1、子はそれぞれ6分の1を法定相続することになるのです。
ところで法定相続分に対し、具体的相続分という用語があります。民法903条に規定される特別受益者の相続分の問題です。
被相続人から生前贈与を受けた相続人がいた場合は、相続開始時に存在した相続財産の価額に、その相続人が生前に受けた贈与の価額を加えたものを、相続財産とするということです。そして、その価額の中から、受けた生前贈与の額を控除した残額が、生前贈与を受けていた相続人の相続分となるのです。
具体的には、相続人は妻・子A・子B・子Cの4人で、相続時存在したプラスの財産が銀行預金2500万円、マイナスの財産、つまり借金が300万円あり、実は子Aに対し、200万円の生前贈与をしていたとすると、子Aの具体的相続分は200万円となります。
{(2500万円-300万円)+200万円}×1/2×1/3-200万円
=200万円
妻(Aの母)は1200万円、BとCは各自400万円です。
ところで、以前ご説明した平成28年12月に最高裁判所で判例が変更されるまでは、貯金・現金は相続発生と同時に当然各相続人が法定相続分に応じて承継取得し、各自直接金融機関に対して払戻請求ができるとされていました。
この理屈ですと相続発生時には、現金2500万円が存在したのですが、Aが直接銀行に赴いてその6分の1の金額、つまり金416万6666円を引出して取得することができたのです。
ここに挙げた数字に留まる限りは、共同相続人間でさほど大きな争いにはならないかもしれません。しかし子A・Bが相続人で、相続発生時預金が2000万円あるが、実はAが3000万円の生前贈与を受けていたという場合、大きな影響があります。
最高裁判例前 A 1000万円 B 1000万円
最高裁判例後 A 0 B 2000万円
実際の私どもが担当する相続遺産分割事件では、この具体的相続分、つまり特別受益の有無に関する争いが多いです。特別受益分を相続財産に持ち戻すかどうかという意味では、相続財産とみるべきか、つまり相続財産の範囲の問題ともいえます。
このあたりが相続問題解決の解決スタートとなるのです。