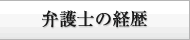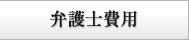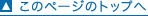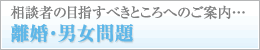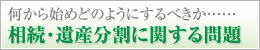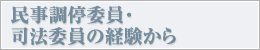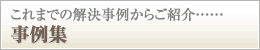ローンで購入した住宅を失うことなく、債務整理ができる方法として、民事再生法の個人版があると聞きました。どのような場合に、利用できるのでしょうか。これが認められた場合、どのような効果が生じますか。
ご質問の手続は、通称個人再生手続という手続きで、住宅ローンを除く負債総額5000万円以内の個人の債務者で、収入を得る見込みのある方であれば、基本的には利用することができます。
その要件や、適用範囲等については、民事再生法221条以下にも規定されております。ここでは、裁判所から選任された個人再生委員としての経験から、留意すべき事柄を、いくつか指摘したいと思います。
まず、個人再生手続(小規模個人再生手続と給与所得者等再生手続の2類型)の申立てにあたり、『住宅資金特別条項の申述』をしなければなりません。
住宅ローンの支払いについて、特別な定めをするという意思表示です。住宅ローン債権者(住宅資金貸付債権者)や、その保証会社が、当該『建物』に、担保権を設定していること、従って、住宅ローンとは関係のない担保権(例えば、事業資金の貸付債権者の根抵当権)が設定されている場合は不可です。
そして現実には、手続開始申立時までに、住宅ローンの期限の利益を喪失していないこと、つまり、約定とおりの支払いを、遅滞せずに履行していることが重要です。
もちろん、期限の利益を喪失していても、申立てはできますが、民事再生規則101条で要件とされる住宅資金貸付債権者との事前協議のハードルが高くなるなど、手続が開始されても、計画弁済が認可されるまでに、紆余曲折が予想されます。
住宅ローン債権以外の一般再生債権については、最低100万円を、原則3年間で弁済することを要しますが、負債総額(基準債権額)と、再生債務者の財産状況(構学上、『清算価値』といいます)から、最高500万円までの弁済を、要することもあります。再生手続が認可されますと、再生債務者は、提出した再生計画通りの弁済をすれば、なんら問題とはなりません。もちろん住宅を維持できます。
個人再生手続の利用者は、増加傾向にあります。これは良いことですが、適用要件をよく理解せずに申立てをされ、「こんなはずではなかった」となる結果も散見します。まずは、弁護士に相談することが第一です。
最近、電車の広告などで、『過払金返還請求』の案内をよく目にします。実は、私は、5,6年前、事情があってクレジット会社やサラ金から借入れをして、現在も毎月きちんと支払いを続けております。
私がこれら業者に支払ったお金が、戻ってくるということなのでしょうか。。
『過払金』は、利息制限法の制限金利と、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(いわゆる出資法)の罰則が科せられる金利が異なっていたことから生じていた問題です。
すなわち、利息制限法を超過する利息(元本が10万円未満の場合年2割,10万円以上100万円未満の場合年1割8分,100万円以上の場合年1割5分)の支払約束は無効であり、超過利息の支払分は、元本に充当されるのですが、刑事罰を科せられる出資法の金利は、年29.2パーセント超であるため、いわゆるサラ金やクレジット業者は、この間の金利(いわゆる『グレーソーン』)で貸付けを行っており、これが、多重債務が発生した大きな原因でもあったのです。
民法上、無効な支払いは不要です。そこで、利息制限法を超過する利息分を、順次元本に充当していく計算(これを『法定金利計算』という)をした結果、もはや貸金残はなく、『払い過ぎ』になっていたケースが認められます。
長期にわたって無効な金利を支払っていれば、より過払いとなる可能性が高く、経験上、サラ金側の請求残高が50万円、取引期間が5~6年で、ほぼ残高0となると予想が立つものです。
もっとも、たとえ一社過払いが発生していたとしても、問題は解決しないことはあります。
たとえば、過払金として50万円戻ってきても、なお別の債務が200万円あって、安定した収入がない場合などは、破産手続開始決定申立てなどが避けられないでしょう。
また、過払金があるかどうかは、正確な取引経過を検証しなければならず、その前提として、債権債務の処理のため、弁護士等専門家が入って、約定の支払いをストップさせるため、いわゆる信用情報(ブラックリスト,『破産について』を参照)に登載される可能性はあります。
ただし、たとえ過払いになっていたとしても、お金を借りたこと自体は、考えなければなりません。その意味で、「もうお金は借りられない」という信用情報(ブラックリスト情報)を、マイナスと感じるのは、疑問があるところです。そして、『きちんと支払っている』の実態が、他からの借入金で賄っていたのであれば、『借りまくっている』のです。
いずれにしても、借入れの事実があるのでしたら、弁護士等にご相談すべきです。