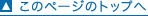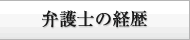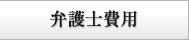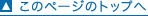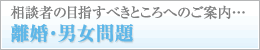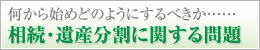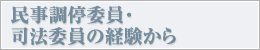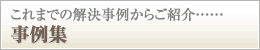事例 刑事・少年事件、犯罪被害一覧
家庭裁判所に係る実務で、最も『実効性』が難しいのは面会交流です。
ここに実効性と書いたのは、仮に調停が成立し、また審判が確定しても、そのとおりに面交が実現するとは限らないからです。
未成年の子と離れて暮らす親、これを非監護親と言いますが、子を監護する親が協力しなければ面交は実現されません。幼い子どもが非監護親のもとにひとりで行き来することはありませんから。
それと裁判所は、調停委員会も含めて言うことは立派で正しいが、司法手続を離れた後の面交の実情については、ほとんど理解しておりません。理解しているとしても、司法手続以外の事柄に、手を差し伸べてくれません。弁護士が必要な理由が、ここにもあります。
弁護士が当事者の代理人として関与しない調停や審判では、本質的に子を別れた非監護親と会わせたくないと考えている監護親は、この場さえ切り抜ければよいと思っています。昔は、「子が会いたいと言えば会わす」というふざけた答弁が少なくなかったのですが、最近では「裁判所で決まった(決められた)ことは守る」というものが見受けられます。
こんなケースで、「月1回、日時・場所・受渡しの方法は、子の利益を考慮して当事者誠実に協議して決定する。」程度の調停条項や、審判にされるのがオチです。協議協力なんかするはずがない。
私は、裁量の余地のない面会条項を作成合意しなければならないと、常々申しておりました。当事者が「協議」するまでもなく、いわば機械的に行うかたちです。
そして最近では、監護親が逃げられない、拒否できない面交条項又は審判決定を得ることを希求しています。
裁判所は、間接強制が可能となる条項や審判を嫌います。
間接強制とは、「・・・のかたちで面交させなければならない」と定めたうえ、もし監護親がこれを守らないときは、地方裁判所に強制執行の申立てをし、これを受けた裁判所が、「・・・しないときは、不履行1回について金〇〇円を支払え」などと命じ、心理的に面交をせざるを得ない状況を作ることを言います。
この間接強制ができれば、できるような審判となっていれば、実行可能性は高まります。しかし家裁は嫌がります。一度もしたことがないと言って、憚らない裁判官もおりました。
とするなら間接強制によらず、事実上監護親が面交実行から逃げられない条項や、審判を求める必要があるのです。ここ数年の間に私は、何回かこれを経験し、獲得してきました。折を見てその実務をお話ししたいと思います。
まずは面交を求めながら、あるいは面交ができる調停・審判がありながら実現できない非監護親の方は、どうぞご相談にお越しください。
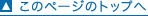
息子さんは、おそらく恐喝罪にあたるとして捜査の対象とされ、逮捕されたのでしょう。
息子さんは、14歳以上ですから、『犯罪少年』とされ、少年法の適用を受け、家庭裁判所において審判を受けることになります。ただし、家庭裁判所に少年事件(保護事件といいます)が送致されるまでは、成人の刑事手続と同様捜査が行われ、逮捕勾留され、取調べも受けます。
ですから、まず、少年が、犯罪の嫌疑をかけられたら、まして身柄拘束されたら、成人のケース以上に、弁護士に依頼する必要性が高いのです。
そして10日間の勾留の後、検察庁は、捜査記録とともに、息子さんを家庭裁判所に送致します。送致を受けた家庭裁判所では、審判(成人の判決に相当する)するについて、家庭裁判所調査官の調査に付されるか、少年鑑別所に送るかを決めます。これを『観護措置』といいますが、ここで鑑別所送致決定を受けなければ、審判において、『少年院』の決定は、まずないと考えられます。
そこで、弁護士(家庭裁判所の手続に入ると『付添人』といいます)から、鑑別所送致は不要であることを言ってもらい、並行して、在学校に報告し、理解を得ることが、とても大切です。
被害者への謝罪・示談も同様です。なお、少年鑑別所入所期間は、最大で4週間です。
このようにして、調査、鑑別を受け、息子さんは、家庭裁判所で、審判を受けることになります。非行事実の存否、軽重も重要ですが、少年法では、『要保護性』を重視します。
すなわち、ご両親や学校等、お子様を支える環境が万全であることを裁判所に理解してもらう必要があるのです。恐喝の事案ですと、①少年院送致 ②保護観察 ③不処分(非行事実はあっても、処分しないという場合を含む)が、考えられます。
息子さんは、不安でいっぱいの心境だと思われます。一刻も早く、弁護士を付けてあげてください。
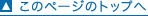
裁判員制度の施行を前にして、鹿児島県議買収事件,富山強姦事件などで、報道を聞く限り信じられない無罪事件が相次ぎました。
なぜこんなことが起きるかと言えば、捜査機関の見込み(思い上がりと言ってもよいかもしれません)と、自白に依存する捜査手法が存在するからです。
鹿児島の事件でも、富山の事件でも、アリバイは取り上げられませんでした。
ご質問者に偽証罪が成立する余地はありません。法廷で宣誓した証人が、自己の記憶に反した事実を述べた場合が、偽証罪の成立要件です。
ただ、ご質問者が黙っていれば、あるいは, アリバイの説明を担当刑事が黙殺したら、Aにとって、取り返しのつかない事態に至る可能性があります。
Aには、刑事弁護人が就いていないと思われます。起訴前には、全ての事件で、国選弁護人が選任されるものではないからです。
まずご質問者は、地元の弁護士会の人権擁護を扱う係に事情を訴えてください。
罪を犯していない人間が処罰されるかもしれない状況にあることに加え、ご質問者自身、『偽証罪・・・』などと威嚇されて、真実を述べる機会を封じ込められようとしているのですから。弁護士会が、これを取り上げて動きます。
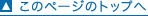
たいへんお苦しいお気持ちの中で、ご自身で判断し、行動することは止めましょう。どうしたらよいかわからないとき、あなたをサポートする人が必要です。
犯罪が発生した場合、それがいかに凶悪なものであっても、私人が取り締まりをすることや、処罰をすることはできません。近代司法は、復讐を禁止しております。
罪を犯した者,これを『被疑者』と言いますが、被疑者について、いかに処罰を求めるかの権限は、社会秩序の維持・観点から、公益の代表者である検察官の専権です。
ところが日本は、犯罪被害者の支援が不十分な状況下で、警察の捜査や検察の事件処理が行なわれるため、被害者に対する取扱いの酷さが指摘されてきました。そして、これが『二次的被害』と受け止められるようにもなり、犯罪被害者も、刑事司法に参加する制度が生まれました。
すなわち、検察官は、犯罪被害者の応報感情の充足をすることを職責にしないので、検察官と異なる立場で、公判において意見を述べることが、犯罪被害者参加制度なのです(刑事訴訟法316条の33以下)。
つまり、あなたが犯罪被害者参加制度を利用すると、ご自身の立場で、積極的に意思を表明し、犯人(被疑者が起訴された場合、『被告人』と言います)に対する量刑について、公判で述べることが可能となります。
しかし、現状では、そのような確固たる意思にまでは至らず、被告人の弁護人からの連絡に当惑し、混乱しているというのが実情ではないでしょうか。
そのような状況にある場合は、犯罪被害者として、弁護士のサポートを受けてください。あなたの依頼を受けた弁護士が、あなたに代わって、被告人の弁護人の話を聞き、やり取りをしてくれますし、犯罪被害者の心情を十分理解し、この先経験するであろう諸々の手続等にも精通した弁護士が側にいてくれるだけでも、不安が解消されるのではないでしょうか。
やがて気持ちが落ち着きましたら、弁護士を介して、被告人の弁護人に対して言いたいこと,思うところを伝えてもらいます。
もし、公判に、犯罪被害者として参加したいと考えられたのでしたら、弁護士と一緒に出頭しましょう。検察官との交渉も担当するので、論告求刑にも、犯罪者の主張を量刑の一事由として考慮されることがあるでしょう。
加害者被告人の弁護人からの連絡に対し、返答しないことと、返答できないことは、意味が違います。「今は答えられる状況にない」と言うだけでも、弁護士を通じて回答しておけば、弁護人も、犯罪被害者に対するアプローチの仕方を気に掛けると思います。
あなたに弁護士が就くということは、「被害者を蔑ろにすることは許されない」と、被告人が気付く可能性もあります。気持ちが整理できる状況になりましたら、あなたの弁護士を介して、被告人の状況,公判の進行等が報告され、あなた自身で監視していくこととなるでしょう。ご検討ください。