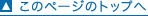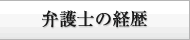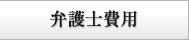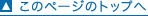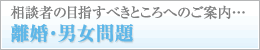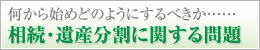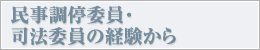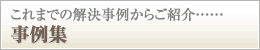相続・遺産分割に関する問題一覧
相続に関する初回相談をお受けするとき、たいてい相続人のうちお一人がいらっしゃいます。
相続人が一人なら紛争は生じません。また相続人が2名で、両名間に争いがあって相談に来られた場合は、相談者(依頼者)と相手方が当事者ですから、相談者の希望を承り、その実現可能性とプロセスをご説明すればよいのです。
問題は、複数の相続人、要は3人以上の相続人がいて、その中のお一人から相談を受けた場合です。
例えば、父の相続が発生し、相続人は母と弟というケースで、遺言はなく、相続財産は預貯金と父母が住む土地建物だったケースで、「兄」から相談を受けた場合を例にします。
相談者である兄は、不動産はそこで生活する母が相続し、自分は預貯金を相続したい希望があり、加えて「弟も同じ考えだ」と言った場合です。
この場合、弟が本当にそのような希望があるかはわかりません。仮に、兄が弟から「兄貴に任せる」と言われたと説明しても、それだけで兄弟両名から委任を受けることはありません。
いつも申しますとおり、必ず「依頼者」と面談して、委任契約を締結することは当然です。
これに加えて相続の場合、兄弟間で、相続人間で利害が対立する可能性が常にあるからです。例えば、後になって「弟」が、自分も不動産が欲しいと言うかもしれません。また実は「兄」には、母から少なくない生前贈与がなされていたと発覚するかもしれない。
つまり仮に弁護士が、兄弟両名から依頼を受けた場合、両人間に対立が生じれば、職務遂行が不可能となってしまいます。
私は、相続・遺産分割事件で、複数の相続人がいる場合は、その中のお一人と委任契約を締結します。とは言え、そういう理屈はわかっていただいても、利害対立が生じる恐れがほとんどない場合で、絶対にそうしなければならないのは、ある意味法的サービスに欠けます。
このようなケースでは、私の知り合いの弁護士をご紹介することがあります。
また、私が複数の相続人から――当然面談打合せをした上で――委任を受け場合でも、当然委任契約はそれぞれ締結しますし、費用もそれぞれ頂戴します。
また最後まで利害対立なく、例えば遺産分割調停が成立するときでも、了解いただいて調停成立の場で、両人又はどちらかの手続代理人を――調停調書上――辞任したかたちにするなど、諸々の手当をいたします。
私が相続・遺産分割事件を担当してしばしば目にするのは、相手方は複数いるのに同じ代理人が就いているケースで、これはその中のある一人の考え希望で進められているケースです。
例えば先の例で、私の依頼者が兄、相手方となる母と弟には同じ代理人弁護士が就いている場合、相手方代理人より不動産を売却処分したい旨申し出られたとします。その場合、果たして母は、居住する不動産を手放すこと、他所で生活することを本当に望んでいるのだろうかの疑問が出てきます。
これは弟の意思によって進められているのではないか、母は本当に、理解しているのかという疑問です。
母がある日、「不動産を手放したくない」意思を表明したら、母と弟の両名から委任を受けた弁護士は、辞任しなければなりません。つまり、最初からやり直しです。
最初に戻ります。初回無料相談にお越しになる方は、たいていお一人です。
もちろんそのお一人のために回答し、ご助言し、より良き方向性をお示しします。加えて、「他の相続人は、どのようなお考えですか。」と尋ねます。
他の相続人からも、お話を伺うことはいたします。それぞれの意思を希望を確認し、弁護士として、やはり最初に相談に来られた方のみの代理人を務めさせていただくことを申し上げることがほとんどです。
一般的に、紛争を解決しようと動いた方の意思は固いと思われます。「誰かに任せた」をそのまま信じ受け容れて、よい仕事ができるとは思われないからです。
ある意味相続は、早く動いた人の勝ちとなることが往々にしてあるのです。また、先送りはいけません。
相続・遺産分割に関する相談は、早めにおこなうことをお勧めいたします。
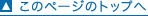
相続とこれに続く遺産分割事件では、考察・検討すべきは以下の順序です。
最初は、相続人の確定です。誰が相続人か、普通はわかっていると思いますが、遺産分割協議は、全相続人で行わなければなりません。そうでなければ、例え協議書に調印しても、登記手続や預貯金の引出しはできません。
よく言われる被相続人の出生から、相続発生時までの全ての戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)を取り付ける必要があります。
次に、相続財産の範囲を確定します。実は、ここが結構争いになります。
「相続財産」は、生前贈与を受けたものは戻されてカウントされますし、例えば被相続人が契約者の保険や退職金等は、税務と異なります。
また名義は、他の人(例えば相続人のうちの誰か)であっても、その原資を出したとか、個人のお金で会社名義で運用していたようなケースもあります。
具体的な分割の話を行うにあたり、「相続税が発生するかどうか」は、とても大切なポイントです。相続税の納付を要するような相続が起きた場合は、当然納付期限(10ヵ月)までに、税理士に委任して申告書を出します。
その場合の「相続財産」は、相続発生時の被相続人名義の財産となっています。ここで、およその相続財産の範囲(目星)とその価額が見えてきます。
相続税の申告時までに、遺産分割を完了しなければならないものではありません。ここもよく誤解されるところです。法定相続分に応じた未分割の状態で、申告することが少なくありません。
この場合3年程度の間に、相続人間で、具体的な遺産分割協議が成立する見込みである旨弁護士の上申書を添付すると、後日修正更生申告により対応することができます。
私たち弁護士が、一番初めに目をつけるのは、相続税の申告が必要な相続かどうかです。
定額控除が3000万円に、600万円×法定相続人数が、相続税がかからない相続財産です。ですから、例えば相続人が2名で、合計4000万円を超える相続財産があると思われるときは、まず申告を急ぎます。
相続税の評価と、遺産分割時の相続財産の評価は、同じではありません。しかし申告書控は、極めて重要な資料です。
少なくとも家庭裁判所での遺産分割調停、そして審判には、必ずその添付を要します。裏返して言えば、相続税が発生する相続・遺産分割のケースでは、申告と納税なくしてその先の手続、すなわち具体的な相続財産の分割には進まないということです。
相続税の申告をするとき、その財産の存在を示す資料の添付が求められます。
不動産登記簿謄本・通帳写し・有価証券取引明細書等です。これらを手掛かりに、遺産分割協議を進めます。
相続税が発生しない相続の場合は、もちろん申告は不要です。従って何が相続財産かは、被相続人と一緒に暮らしていたとか、事実上介護・監護していた人を中心に情報を出し合って、確認確定していくほかありません。
預貯金は遺産共有となり、全相続人による遺産分割協議が成立するまで、解約引出しはできません。
また不動産についても、法定相続によらない登記、例えば母と子が相続人の場合、母を4分の3、子を4分の1とする相続登記は、子の同意(押印)なくしてできません。
かと言って、法定相続に従った各共有持分登記をしてしまったら、「遺産分割」はできなくなり、「共有物分割請求」という厄介な手続に進まざるを得なくなります。
相続問題は、先送りしてはいけません。
自分の代で解決させるという姿勢が大切です。手順は上記のとおりですが、これに従って具体的な分割手続と履行がなされるかは、簡単ではないはずです。
相続財産があることに感謝して、これを受け生かすために、是非とも早期に、特に納税時期前に、弁護士に相談・依頼することをお勧めします。
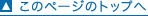
相続が発生すると遺産分けをする前に、税金をどうする、申告をしなければと考えられる方が少なくないと思います。
相続税が発生しないケースは、そうではないのかもしれませんが、プラスの相続財産が存在する場合は、相続・遺産分割は、必ず履践しなければならないとお考えください。
平成28年に裁判例が変わり、預貯金については、「遺産共有」という実務になったと申しました。
公正証書遺言で、預貯金口座が明確に特定され、ただひとりの相続人が、全遺産を相続する内容にでもなっていれば、金融機関は遺言どおり対応するかもしれません。
しかし、全相続人の同意・協議により預貯金の分配が決まらない限り、金融機関は、相続財産である預貯金の解約・引出しには応じません。
ところが不動産については、各相続人が法定相続分に従った相続を原因とする持分移転登記が可能です。いわゆる共有登記となり、これの解消は遺産分割ではなく、共有物分割請求手続となります。
前回までに、これはご説明いたしました。
預貯金口座が相続発生により凍結されてしまったら、もし多額の預貯金が存在したならば、共同相続人としても「何とかしたい」、つまり遺産分割協議を成立させたいと考えるかもしれません。
しかし、不動産についてはこれまでご説明したとおり、決して持分に対応した共有登記をすべきではありません。特に、相続人名義のままで困らないケースも少なくないと思われます。
昨今しばしば報道される「空家問題」もあります。
相続発生により、相続財産である土地建物を使用する人がいなくなり、その不動産が相続人にとって遠方にあって利用する可能性がない、あるいは資産性がなく、維持費がかかってしまうケースなどでは、むしろ「そのまま」にしておく、面倒を避けたいのが相続人の大半の見解ではないでしょか。
こうして被相続人名義、つまり亡くなった人の登記名義のまま残された不動産が、全国に存在しているのです。
令和3年4月21日参議院で、民法及び不動産登記法の改定が議決され、法律として成立しました。
これは、空家問題等として所有者がわからない不動産の放置を、発生させないことを目的としたもので、不動産の相続を知った後、3年以内に相続を原因とする所有権移転登記を行うことや、引っ越し等で住所が変わった後、2年以内の表示変更登記を行うことなどを義務付けし、違反者には過料を科す内容となっています。
過料を科せられたらいやですから、不動産の相続登記は進むと思います。
しかし、すぐに遺産分割が成立するわけではありませんし、かと言って、とりあえず持分に応じた共有登記をしてしまうと、繰り返し申し上げるとおり、もはや「遺産」ではなくなり、これの分割は、地方裁判所で共有物分割請求訴訟で決めることになっています。
また遺産分割協議が整わない場合は、10年経過したら決定相続によると決められたようです。
この法改正は、あくまで空家問題等の観点から導かれたものですが、「問題の先送りはしてはならない。」と申し上げたところをさらに加速させるものです。
相続が発生したら、相続税がどうのを考える前に、まずは弁護士にご相談ください。「遺産分割」手続を、必ず進めなければならないとお考えいただく必要があるからです。
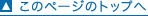
遺産分割は、相続人の確定、遺産の範囲の確定がなされると、その遺産の評価を行います。
遺産の評価としてしばしば争いになるのは、不動産、特に土地です。
不動産の評価は、分割時点での時価を基準とします。これが教科書的な回答です。時価とは、不特定多数の人の間で、通常の自由な取引がなされるとした場合に用いられる代金額を意味します。
相続発生から実際の分割時期までに、時間を要することもあります。そして様々な事情で、相続発生時と分割がされようとする現在とでは、価格がかなり変わるケースもあるでしょう。でも基本は、現在の分割時とされる例です。
そして何を基準にするかで、常に争いになります。
時価といっても、現実にその不動産を売りに出すわけではありませんから、売買契約が行われるときの売出価格、あるいは成約価格を意味するものでもないのです。
何をもって「時価」とするのか。実務上は、各不動産会社から取り寄せた査定書のオンパレードになることが、少なくないです。
そこで裁判所では、国土交通省が毎年1月1日現在の都市及びその周辺地域の標準値の地価として発表する「公示価格」を出すよう求めます。
公示価格は、一応その標準値について、自由取引が行われる場合の正当な価格を計算したものとされていて、これを基に相続税や固定資産税を決定すると扱われているからです。
もっとも全ての土地に、公示価格が示されるわけではありません。まさしく標準地しか発表されないので、その場所からの距離・地域性(商業地域か低層住宅地かなど)、そして地形などが違えば、基準としては使いにくいでしょう。
ある程度客観性という点では、相続税を申告する際に用いられる路線価、また、固定資産税を課するための評価としての固定資産税評価額も利用されることがあります。
ただし相続、そして固定資産税評価額は時価より低いので、固定資産税評価額に0.7を割り算するよう算式が用いられたり、1.2倍にするなど調整されることがあります。
路線価と時価は、地域にもよりますが、近時は大きな差は見られない傾向にあります。しかし路線価とは、まさしく路線、すなわち道路に面している土地を対象とします。で、これまた利用しにくいケースがあるのです。ただ裁判所の調停では、相続税の申告書があるケースでは、まず路線価に従った財産表を作成する実務です。
こうしてみると、時価といっても基準とするものはないに等しいことに気付きます。要するに「時価」とは、あくまで講学上机上の概念であり、実際の遺産分割の場面では、いろいろな要因により当事者双方が合意できる評価額を、決めていく作業がなされるとしか言いようがありません。
なお合意できず、審判等になるにあたっては、裁判所による鑑定が利用されることがあります。ただし、これを利用するには、出された鑑定価格を当事者は受け容れるよう、予め裁判所から求められることが少なくありません。
鑑定をしても、また争われたらその意味がないとの判断でしょう。しかし私は、これまでの経験から、決してお勧めいたしません。
不動産の「時価」とは何か。それは決して教科書どおりには収まりません。
しかし実際の調停・審判では、収まるところに収まります。
ここではまさしく机上でありますから、実際の遺産分割例に携わってきた経験と申し上げておきます。
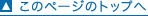
相続が発生すると遺産分けをする前に、税金をどうする、申告をしなければと考えられる方が少なくないと思います。
相続税が発生しないケースは、そうではないのかもしれませんが、プラスの相続財産が存在する場合は、相続・遺産分割は、必ず履践しなければならないとお考えください。
平成28年に裁判例が変わり、預貯金については、「遺産共有」という実務になったと申しました。
公正証書遺言で、預貯金口座が明確に特定され、ただひとりの相続人が、全遺産を相続する内容にでもなっていれば、金融機関は遺言どおり対応するかもしれません。
しかし、全相続人の同意・協議により預貯金の分配が決まらない限り、金融機関は、相続財産である預貯金の解約・引出しには応じません。
ところが不動産については、各相続人が法定相続分に従った相続を原因とする持分移転登記が可能です。いわゆる共有登記となり、これの解消は遺産分割ではなく、共有物分割請求手続となります。
前回までに、これはご説明いたしました。
預貯金口座が相続発生により凍結されてしまったら、もし多額の預貯金が存在したならば、共同相続人としても「何とかしたい」、つまり遺産分割協議を成立させたいと考えるかもしれません。
しかし、不動産についてはこれまでご説明したとおり、決して持分に対応した共有登記をすべきではありません。特に、相続人名義のままで困らないケースも少なくないと思われます。
昨今しばしば報道される「空家問題」もあります。
相続発生により、相続財産である土地建物を使用する人がいなくなり、その不動産が相続人にとって遠方にあって利用する可能性がない、あるいは資産性がなく、維持費がかかってしまうケースなどでは、むしろ「そのまま」にしておく、面倒を避けたいのが相続人の大半の見解ではないでしょか。
こうして被相続人名義、つまり亡くなった人の登記名義のまま残された不動産が、全国に存在しているのです。
令和3年4月21日参議院で、民法及び不動産登記法の改定が議決され、法律として成立しました。
これは、空家問題等として所有者がわからない不動産の放置を、発生させないことを目的としたもので、不動産の相続を知った後、3年以内に相続を原因とする所有権移転登記を行うことや、引っ越し等で住所が変わった後、2年以内の表示変更登記を行うことなどを義務付けし、違反者には過料を科す内容となっています。
過料を科せられたらいやですから、不動産の相続登記は進むと思います。
しかし、すぐに遺産分割が成立するわけではありませんし、かと言って、とりあえず持分に応じた共有登記をしてしまうと、繰り返し申し上げるとおり、もはや「遺産」ではなくなり、これの分割は、地方裁判所で共有物分割請求訴訟で決めることになっています。
また遺産分割協議が整わない場合は、10年経過したら決定相続によると決められたようです。
この法改正は、あくまで空家問題等の観点から導かれたものですが、「問題の先送りはしてはならない。」と申し上げたところをさらに加速させるものです。
相続が発生したら、相続税がどうのを考える前に、まずは弁護士にご相談ください。「遺産分割」手続を、必ず進めなければならないとお考えいただく必要があるからです。
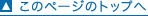
平成28年12月の最高裁の判例により、相続発生によって当然に法定相続分に従った「遺産分割」にはならず、「遺産共有」となることをご説明しました。
この遺産共有は、預貯金について意義がありました。
それは、法定相続分に従って当然分割になり、各相続人が金融機関に対して預金の引出しを求めて取得することが、その人に対して生前贈与などがなされていた場合に、共同相続人間に不公平が生じるからでした。
しかし不動産については、法定相続に対応した共有登記をすることが認められています。つまり、法定相続人の誰かが、法定相続分を各持分とした相続を原因とする移転登記をすることは、実務上可能です。
それは、とりあえず相続人に登記を移しておく、つまり保存した状態にして、これからゆっくりこれをどのように分けるか、遺産分割の協議をしよう…と思われるかもしれません。
しかし、それはできないのです。不動産に共有関係が生じたら、要するに共有持分登記が現れたら、その原因が何であれ、その『共有関係』を解消するには、共有物分割請求によるしかないのです。
世の中には、共有関係が生じることがあります。例えば夫婦で不動産を購入して、持分登記をするとか、何らかの組合が存在して、各組合員が持分を有するとか、建物建築ができるよう、公道につながる『私道』が共有関係になっているとかいくつもあり得ます。
つまり、相続だけが共有を生むわけではないのです。民法では、共有状態の解消という観点から、共有物分割請求という制度を執っています。
共有関係の解消を求められたら、つまり共有物分割請求を受けたら、どのように分けるかの協議をします。この協議をしないとか、話し合いがまとまらない、うまい分割、つまり共有関係の解消の仕方が導き出せないときには、共有物分割請求訴訟が提起されます。
共有物分割請求訴訟の中で、話し合いがまとまればよいですが、それも無理な場合は、裁判所は当該不動産について、競売を命じます。競売をして、手続費用を控除して、買受人から支払われた『売買代金』を、各共有持分に応じて分配することになります。
共有物分割請求訴訟の判決主文は、競売に付することを決定するに留まり、確定判決に基づいて別途競売申立てが必要です。
さて『遺産共有』状態にあるから、ひとまず相続人間の持分に応じた共有関係にしてしまうと、もはや『遺産分割』手続はできなくなります。
遺産分割の管轄は家庭裁判所で、調停・審判と進みますが、共有物分割は地方裁判所の裁判、そして判決となります。
共有状態が生じた理由は関係ないので、遺産である不動産を共有登記(持分登記)にしてしまったら、実務上遺産ではなくなります。
複数の遺産があって、かたや預貯金は遺産分割、不動産は共有物分割に手続きが変わるのは、非合理的です。
遺産の中に不動産が存在する場合、急ぎ持分登記をしないよう注意する必要があります。
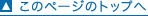
被相続人(亡くなった方)の財産を、相続財産又は遺産と言います。相続開始により遺産は、法定相続人の間で共有関係になります。
なお、遺言により法定相続人ではない人に、遺産の全部・一部を贈ることを遺贈と言い、受ける人を受遺者と言いますが、この場合の受遺者と法定相続人の関係は、機会を改めてご説明いたします。
最高裁判所の判例変更により、法定相続人が複数存在する場合は、遺産について抽象的観念的に、共有関係が生じます。これを遺産共有と言うことがあります。
最高裁判例が出される平成28年12月より前の実務は、預貯金については、相続開始により当然法定相続分に応じて分割される、つまり相続人は、各自法定相続分に応じた被相続人名義の預貯金を、直接金融機関から支払いを受けることができたと申しました。
ところが、上記判例変更により相続開始と同時に預金についても遺産共有関係が生じ、相続人間でこれの分割協議が整わない限り、金融機関は解約・引出しには応じなくなりました。
では、不動産についてはどうでしょうか。
こちらも遺産分割協議が成立して、相続人のうち誰が相続するか、あるいは誰と誰が持分いくらの共有とするかなどが決まっていれば、そのとおりの相続を原因とする所有権、あるいは持分移転登記手続をすればよいです。
しかし問題は、むしろおかしいおも思えるのですが、不動産登記については、遺産分割協議が成立しない間でも、つまり遺産共有の状態にあるときにも、法定相続分に応じた相続を原因とする移転登記ができるのです。
例えば、父(夫)に相続が発生し、相続人は母(妻)と子2人だとすると、この相続人3名のうち、誰でも父が所有する不動産について母が2分の1、子が4分の1ずつの持分を有する移転登記ができるということです。
つまり遺産共有関係にあり、遺産分割協議が成立していない間にも、『法相続分』に対応した各自持分を有する登記ができ、共有関係が登記簿上も現れるということです。
共有関係が登記簿上生じるだけで、もちろん不動産が現実に分割されたり、処分されるわけではありません。
しかし、相続人各人が、共有持分を有する関係が成立すると、この共有関係を解消し、現実にどのような分割をするかについては『遺産分割』の原則、法文は適用されなくなります。
なぜか。それではどうすればよいか。これについては、次にご説明します。
ここでは、遺産分割協議が成立する前に、法定相続分に従った共有登記にしてはならないという結論だけ覚えてください。
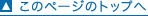
相続が発生した場合、誰が相続人なのかがスタートです。
民法(887条等)に規定があります。配偶者は常に相続人となり、これに並ぶ相続人には順位があります。子が第1順位で、子がいない場合は親、親がいなければ兄弟姉妹となり、常に相続人となる被相続人の配偶者と相続分が定められています。
配偶者と子の場合は、1対1です。相続発生より前に子が死亡していた場合は、その子(被相続人の孫)が子(孫の親)の地位を承継して相続人となります。これを代襲相続と言います。
同順位の相続人間では――例えば被相続人の長男・長女・二女等――法定相続分は同じです。つまり、被相続人の配偶者と子3人が相続人の場合、配偶者が2分の1、子はそれぞれ6分の1を法定相続することになるのです。
ところで法定相続分に対し、具体的相続分という用語があります。民法903条に規定される特別受益者の相続分の問題です。
被相続人から生前贈与を受けた相続人がいた場合は、相続開始時に存在した相続財産の価額に、その相続人が生前に受けた贈与の価額を加えたものを、相続財産とするということです。そして、その価額の中から、受けた生前贈与の額を控除した残額が、生前贈与を受けていた相続人の相続分となるのです。
具体的には、相続人は妻・子A・子B・子Cの4人で、相続時存在したプラスの財産が銀行預金2500万円、マイナスの財産、つまり借金が300万円あり、実は子Aに対し、200万円の生前贈与をしていたとすると、子Aの具体的相続分は200万円となります。
{(2500万円-300万円)+200万円}×1/2×1/3-200万円
=200万円
妻(Aの母)は1200万円、BとCは各自400万円です。
ところで、以前ご説明した平成28年12月に最高裁判所で判例が変更されるまでは、貯金・現金は相続発生と同時に当然各相続人が法定相続分に応じて承継取得し、各自直接金融機関に対して払戻請求ができるとされていました。
この理屈ですと相続発生時には、現金2500万円が存在したのですが、Aが直接銀行に赴いてその6分の1の金額、つまり金416万6666円を引出して取得することができたのです。
ここに挙げた数字に留まる限りは、共同相続人間でさほど大きな争いにはならないかもしれません。しかし子A・Bが相続人で、相続発生時預金が2000万円あるが、実はAが3000万円の生前贈与を受けていたという場合、大きな影響があります。
最高裁判例前 A 1000万円 B 1000万円
最高裁判例後 A 0 B 2000万円
実際の私どもが担当する相続遺産分割事件では、この具体的相続分、つまり特別受益の有無に関する争いが多いです。特別受益分を相続財産に持ち戻すかどうかという意味では、相続財産とみるべきか、つまり相続財産の範囲の問題ともいえます。
このあたりが相続問題解決の解決スタートとなるのです。
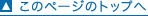
相続とは、故人となられた被相続人の財産などの諸々の権利義務を包括的に承継することです。法人には相続はありません。民法では、法人以外の権利能力がある者を「自然人」といいます。要するに、人・個人と称されるのがこれです。
相続が起きるとまず、「相続人は誰か」を押さえます。民法にも規定があり、順位が定まっています。配偶者は、常に相続人となります。相続人が確定すると、各法定相続分を当てはめます。後に述べますが、私どものところに来られる方の間では、法定相続分で「ドンピシャリ」と決まることは少なく、「具体的相続分」に従って遺産が分割される例です。
相続財産は何か、その範囲(通常遺産の範囲といわれます)が最も問題になることが多いです。仏壇・位牌・墳墓等は、相続財産とはなりません。
相続は、プラス・マイナスの全財産を承継します。親の借金も承継するということです。
相続をしたくない場合、例えば債務のみ残されて、これは被りたくないような場合は、相続放棄の申述という家庭裁判所に許可申出する手続があります。
プラスマイナスが不明な場合、つまり親の財産の範囲で債務は片付けるが、それ以上の対処はしないという場合は、相続人全員で「限定承認」という方法があります。いずれも相続が起きたことを知って、3ヶ月以内に行わなければなりません。
相続人になったあなたが、親に借金があるかもしれないとか、他の相続人との間で遺産分けでもめるかもしれないと思えたなら、「相続財産」に手を付ける前に必ず弁護士にご相談ください。手を付けると、後に放棄ができなくなったり、悪意の果実取得者とみなされるようなこともあるからです。
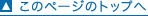
相続と言うと、財産分けだと受け取られますが、そうだとは限りません。
相続発生、即ちご自身が相続人となるご親族が亡くなったとき、何から始め、どのようにしていけばよいのでしょう。
一般的には葬儀をし、並行して各届出をすると思います。最近は、相続発生が確実視された段階から葬儀の仮申し込みを受付け、打ち合わせに応じ費用を試算する葬儀社もあるようです。最初に必要となるのは葬儀費用で、日本の場合火葬しますから、当然費用が0とはならないのです。
後に述べる平成28年12月19日に、最高裁判所が重要な判例を出しました。この判例の実質的意義は別のところにあるのですが、以後相続が発生した場合、被相続人(亡くなった人)の金融機関に対する預金は、引出しできなくなりました(もちろん金融機関が相続の事実を知らなかった場合は、ATM等で下ろすことは可能でしょうが、相続人間で問題となり得るのです。)。
この判例が出されるまでは、預金現金は、相続発生という事実により法律上当然に各相続人の法定相続分に応じて、それぞれが金融機関に申し出て、預金の引出しができる(法律上は、金融機関はこれを拒むことができない)実務でした。故に葬儀代も、被相続人の預金から使うことができたのです。
しかし、本件判例により預金も「遺産共有」となり、遺産分割の合意が成立するまでは、「そのまま」の状態となることが決まりました。
そこで葬儀費用?等当面のためのお金は、相続発生前には用意しておく必要があります。もし被相続人の預金から下ろすのでしたら、他の――推定――相続人にもその措置がわかるような状態にした上で、キャッシュカードを預かるなどして、1日の引出し限度額に注意して準備する必要があります。
この点前記最高裁に判例において、裁判官の中には、立法手当や家裁で行なわれる相続財産中の特定の預貯金債権を、一部相続人に仮に取得させる仮訴分(家事事件手続法200条)の活用に言及する見解はあります。
しかし現実は、前記のとおり相続発生前からの準備が確実です。
因みに一部銀行では、葬儀費用等特定された目的・金額の範囲で、全相続人の同意を要件として、被相続人の預金の引き出しを認める運用がなされております。参考になります。
自身にゆかりのある大切な方とのお別れは、厳かにしっかり行ないたいものです。
「相続問題」は、まず葬儀やこれに続く初七日、四十九日後に対処するのが、後々を考えるとよろしいかと存じます。
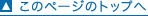
昨年元号が変わりました。三十余年の平成の時代を挟んで、昭和と令和にも弁護士業務を行うことができ、支えてくださった多くの方々に感謝します。
年齢を踏み経験を重ねる過程で、ここ数年の担当業務にも変化・特徴があります。40代のころから男女・親子・家族・家庭に関する案件が増えましたが、ここ数年は相続や遺産に関する事案が相当数を占めるようになりました。
この間私自身も両親の相続を経験しました。これから先は、相続・遺言・遺産分割等について取り扱う機会が増えると予測し、きさらぎ法律事務所のホームページの中にも別稿を設けることといたしました。
相続は、親から子への承継が基本です。少子高齢化社会が進み、介護看護の側面とも絡み、「相続」を予期した親側からの相談のみならず、親をサポートしなければならなくなった子等の側からも、この程相談を受けることがあります。
相談とは民法でいえば、「権利能力の喪失」でもあり、有り体に言えば「人の死」です。どのように生き、終焉を迎えるか、人生観・世界観はたまた宗教観からも、様々な希望や意見を賜ることがあります。
楽して自由に生き誰にも迷惑かけず、自分が亡くなった後も残された人に争いが起きないようにと願う方がほとんどです。
しかし、残念ながらそうはいかない現代日本の現実です。
どのような立場、どのような状態の方であっても、私はまず、ゆっくりしっかりお話を聞くことから始めます。どうぞきさらぎ法律事務所にお越しください。随時この稿に書いてまいります。